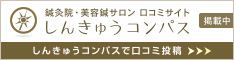四季がはっきりと感じられる日本では、季節の変わり目に体調を崩しがちな方も多いのではないでしょうか。特に寒暖差が大きい春や秋は、自律神経が乱れやすく、頭痛や肩こり、眠りの質の低下などで悩まれる方が増えます。そんな季節ごとの体調管理に役立つのが、古くから伝わる「二十四節気(にじゅうしせっき)」を基本とした養生法です。今回は、霧島市で鍼灸マッサージ院を営む私たち青空堂はりきゅうマッサージ院が、二十四節気に合わせた養生法と、季節の変わり目におすすめの鍼灸ケアについて丁寧にご紹介します。
二十四節気とは?
二十四節気は、中国で約2000年前に制定された暦のひとつで、1年を24の期間に分けて季節の変化を細かく捉えるものです。これにより、農作業や生活のリズムを季節に合わせることができました。日本においても古くから重要視され、季節の養生に深く結びついています。
二十四節気の主な特徴
一年を約15日ずつ区切ることで、春夏秋冬の節目だけでなく、細かな気候変化や自然現象の変わり目を把握できます。例えば、立春、春分、立夏、秋分、立冬などが代表的な節気です。これらの節気に応じて、身体や心の調子を整える養生法が伝えられてきました。
特に季節の変わり目は環境の変化や気圧の変動、気温差などが大きいため、自律神経が乱れやすく、身体の不調が起きやすい時期といえます。この時期に体調を崩さないためには、「二十四節気に合わせた養生」が有効です。
二十四節気の活用で心身のバランスを整える
季節ごとに変わる体の状態を理解し、それに合った生活習慣や食事、鍼灸ケアを取り入れることで、体調不良を未然に防げます。東洋医学の観点からは、体内の気(エネルギー)の流れや臓腑の働きにも季節の影響が強く反映されると考えられています。したがって、二十四節気を意識した養生は、それぞれの時期に合った体質改善や健康維持につながるのです。
季節の変わり目に崩しやすい体調とは?

春や秋の変わり目には、寒暖差や気圧の変化が激しく、自律神経のバランスが乱れやすくなります。その結果、次のような不調が現れがちです。
主な症状
・頭痛や偏頭痛
・肩こり、首のこり
・腰痛などの慢性的な痛み
・身体のむくみ
・不眠や睡眠の質低下
・だるさや疲労感
・食欲不振や胃腸の不調
これらの症状は、病気とは言えないものの日常生活に大きな影響を及ぼします。生活の質(QOL)が下がる原因となり、長期化するとさらなる体調悪化を招くこともあるため、早めの対策が重要です。
季節の悪影響を受けやすい理由
季節の変わり目は外気温だけでなく、湿度や気圧も大きく変動します。人体は環境変化に適応するため自律神経が活発に働くものの、過度な変化は内臓や筋肉の緊張を生み、血流悪化やホルモンバランスの乱れを起こします。また、冬季から春への移行期では「肝」の機能が関係すると東洋医学では見なされ、肝の不調が身体のだるさやイライラにつながることもあります。
鍼灸は、こうしたバランスの乱れを調整し、自然治癒力を高めるのに適した施術法です。体質に合わせ季節に合った刺激を加えることで、円滑な気血の流れや臓腑の働きを促します。
二十四節気に合わせた具体的な養生法
ここでは、春分・夏至・秋分・冬至の四大節気を中心に、季節の変わり目におすすめの養生法をご紹介します。暮らしの中に取り入れやすいポイントに注目してください。
春分(3月下旬~4月上旬)/肝を養う時期
春分は陽の気が高まり、体も活動的になる時期です。肝臓の働きが活発になるため、気の巡りを良くし、筋肉や関節のこわばりを緩めましょう。
【養生ポイント】
・軽い運動で血行促進(ウォーキングやストレッチ)
・寝不足やストレスを避けて睡眠を十分にとる
・旬の青菜や苦みのある野菜を摂取
・過剰な飲酒や脂肪の多い食事を控える
・鍼灸で肝経や肩こり・目の疲れをケアする
夏至(6月下旬~7月上旬)/心をケアする時期
夏至は陽の極点で、活動性がピークに達する時期です。暑さで身体が疲れやすくなり、心の不調や眠りの浅さが出やすいので、リラックスを重視しましょう。
【養生ポイント】
・暑さ対策をしっかり行いこまめに水分補給
・神経過敏を抑える柑橘類などの食材摂取
・夜は冷房の効き過ぎや睡眠環境に注意
・マッサージや鍼で心の経絡や背中のこりをほぐす
・笑顔や趣味、深呼吸で気分転換を積極的に
秋分(9月下旬~10月上旬)/肺を整える時期
秋は空気が乾燥しやすく、肺の機能が影響を受ける季節です。呼吸器トラブルや皮膚の乾燥に注意しつつ、身体を潤すことが大切です。
【養生ポイント】
・加湿を心掛けて室内環境を整える
・梨や白キクラゲ、はちみつなど滋養強壮に良い食材を摂る
・唇や肌の乾燥対策もしっかり行う
・鍼で肺経を刺激し呼吸機能や免疫力を高める
・ゆったりした呼吸法やマッサージで体内の潤いを充実させる
冬至(12月下旬~1月上旬)/腎を養い冬に備える時期
冬は身体が内側に熱を溜め込もうとするため「腎」を大切にし、養生することで春先の体調を左右します。寒さに負けず、しっかりと体力を温存しましょう。
【養生ポイント】
・身体を冷やさない工夫(服装や暖房使用)
・黒豆や山芋、クルミなど腎を補う食材摂取
・入浴で温まり血流促進
・鍼灸は腰回りや足の冷えを中心に施術
・睡眠時間を十分に確保し疲労回復に努める
青空堂はりきゅうマッサージ院の季節の鍼灸ケア

当院では、二十四節気の考えを取り入れ、一人ひとりの体質やその時々の季節に応じたオーダーメイドの施術を行っております。
季節に応じた鍼灸施術の特徴
・春は肝経の調整を中心に、肩こりや頭痛の緩和に注力
・夏は心の経絡や自律神経のバランスを整え、疲労回復を促進
・秋は肺経をケアし、呼吸器系の不調予防や肌の乾燥を改善
・冬は腎を補い、腰痛や冷え解消をサポート
これらに加え、筋膜リリースやマッサージを組み合わせることで、血行促進やコリの解消により効果的に働きかけています。
鍼灸が季節の変わり目に効果的な理由
刺激が苦手な方にも配慮したソフトな施術なので、初めての方でも安心して受けられます。鍼灸は、体内の気血の巡りを促進し自律神経のバランスを整えるため、頭痛や肩こり、むくみなどの慢性的な不調改善に適しています。
また季節ごとの養生としての食事や生活習慣のアドバイスも行っており、心身ともに健康的な状態を維持できるサポートをさせていただきます。
日常生活でできる二十四節気の養生習慣
季節に合わせた飲食や生活リズムを意識することが、健康維持に直結します。鍼灸施術と併せて実践しやすい習慣をピックアップしました。
季節の食材を取り入れる
旬の野菜や果物は栄養価が高く、体調を整える力があります。春は苦みのある青菜、夏は清涼感のあるトマトやキュウリ、秋は根菜類やきのこ、冬は黒豆や山芋がおすすめです。
生活リズムを整える
その季節の陽気に合わせて起床・就寝時間や活動量を調節しましょう。たとえば春や夏は朝早く起きて活動的に、秋や冬は無理せず早めに体を休めることが効果的です。
適度な運動やリラクゼーションの習慣化
ウォーキングやストレッチ、呼吸法などを取り入れて、血行促進と自律神経の安定を図ります。また、鍼灸院での定期的な施術も疲労回復やコリ解消に役立ちます。
まとめ
二十四節気に合った養生法は、自然のサイクルと体調を調和させるための大切なヒントです。季節の変わり目は体調を崩しやすい時期ですが、食事や生活リズムの見直しと併せて、鍼灸を活用することで不調を抑え、より快適な毎日を過ごせます。
霧島市の青空堂はりきゅうマッサージ院では、季節ごとの身体の状態に寄り添い、痛みや不調の根本改善を目指した施術をご提供しています。頭痛や肩こり、腰痛、むくみ、さらには美容鍼のリフトアップまで幅広く対応可能です。季節の変わり目でお身体の調子が優れない方は、ぜひ一度ご相談ください。皆さまが健やかに過ごせるよう、心を込めてサポートいたします。
季節の変化を味方につけ、心身ともに元気な毎日を迎えましょう!