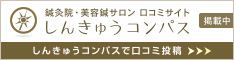月経前のイライラや腹痛、生理中の強い痛みに毎月悩まされていませんか。PMS(月経前症候群)や月経痛は、ホルモンバランスの乱れや血行不良、自律神経の乱れなどが関係しており、日常生活に大きなストレスをもたらします。当院でも多くの女性が「来院前は鎮痛剤が手放せなかった」「仕事や家事に支障が出ていた」とお話しされます。そんな方におすすめしたいのが、鍼灸を取り入れたケアです。痛みのない、そして快適な生理周期を目指すための方法を詳しくご紹介します。
PMS・月経痛の症状
月経前後に現れる不快症状は、単なる「生理痛」だけではありません。体質や生活習慣によって現れる症状は多岐にわたり、重い場合は日常生活に支障をきたすほどです。まずは代表的な原因を押さえましょう。
1. ホルモンバランスの乱れ
月経周期に伴うエストロゲンとプロゲステロンの変動が神経伝達物質に影響し、情緒不安定や頭痛、乳房の張りなどを引き起こします。特にプロゲステロンが急増する黄体期に症状が強くなる傾向があります。
2. 血行不良
骨盤周辺の血流が滞ることで、子宮筋や腰部の筋肉に酸素や栄養が不足し、痛みや冷えを感じやすくなります。冷え性や運動不足の方ほどリスクが高いと言われています。
3. 自律神経の乱れ
ストレスや過度な疲労が交感神経と副交感神経のバランスを崩し、痛みの閾値を下げる原因に。睡眠不足や不規則な生活リズムが追い打ちをかけることも。
鍼灸で期待できる効果

鍼灸は、経絡やツボに刺激を与えることで全身のバランスを整え、自然治癒力を高める東洋医学の手法です。PMS・月経痛に対しては次のような効果が期待できます。
ホルモンバランスの調整
お腹や腰のツボに鍼を施すことで、ホルモン分泌を司る自律神経系に働きかけ、エストロゲンとプロゲステロンの調和を取り戻しやすくします。周期に合わせた施術タイミングで、排卵前後や月経初期の症状軽減が見込めます。
血行促進と筋緊張緩和
経絡上のツボを刺激すると、血管が拡張し、子宮や骨盤内の血流がスムーズになります。これにより筋肉のこわばりがほぐれ、痛みの原因となる乳酸などの老廃物も排出されやすくなります。
自律神経の安定
背部や手足のツボに鍼灸を組み合わせることで、交感神経の過剰な興奮を抑え、副交感神経の働きを高めます。深いリラックス状態に導かれるため、精神的な不安定感やイライラ感も緩和されやすくなります。
当院の施術方法
当院では、鍼灸とあん摩マッサージ指圧師の知見を活かし、PMS・月経痛に特化したオーダーメイドの施術をご提供しています。痛みの少ない細い鍼を使い、筋膜リリースやマッサージを組み合わせることで、体に負担をかけずに全身の調和を図ります。
問診と体質分析
初回は丁寧な問診で症状の時期や強さ、生活習慣などをお伺いし、体質やストレス要因を探ります。これにより、個々のバランスに合わせたツボ選びや施術プランを立てます。
経絡・ツボへのアプローチ
特に子宮周りのツボだけでなく、足の三陰交や内関、背中の腎兪などを用い、ホルモン調整や血行促進に働きかけます。鍼の刺激は心地よい温かさを伴い、多くの方が眠ってしまうほどリラックスできます。
鍼灸とマッサージの組み合わせ
鍼灸後に筋膜リリースや指圧マッサージを行うことで、筋肉の緊張をさらにほぐし、血流促進効果を高めます。施術後は身体が温まり、痛みの軽減だけでなく、全身のだるさや疲労感も解消されやすくなります。
セルフケアのポイント

施術効果を日常で持続させるために、以下のセルフケアを取り入れてみてください。
温活と入浴
38~40℃程度のぬるめのお湯にゆっくり浸かり、下腹部や腰回りを温めましょう。血行が促進され、痛みの緩和につながります。就寝前の半身浴もおすすめです。
適度な運動
ウォーキングやストレッチ、ヨガなど、軽い有酸素運動で骨盤周りの筋肉をほぐし、血流を促進します。過度な運動は逆効果になるため、週に2~3回、30分程度を目安に行いましょう。
食事と生活リズム
ビタミンB群やマグネシウム、鉄分を含む食材を意識して摂取すると、神経機能やホルモン合成をサポートします。また、規則正しい睡眠時間を確保し、スマホやパソコンを就寝1時間前には控える習慣をつけましょう。
まとめ
PMS・月経痛は女性の身体にとって大きな負担ですが、鍼灸を取り入れることでホルモンバランスや血流、自律神経の状態を整え、痛みや不快感を緩和できます。当院では、鍼灸師とマッサージ師が連携し、一人ひとりの症状や体質に合わせたオーダーメイド施術をご提供しています。セルフケアと組み合わせることで、痛みのない快適な生理周期を取り戻しましょう。まずはお気軽にご相談ください。